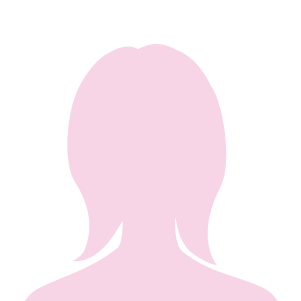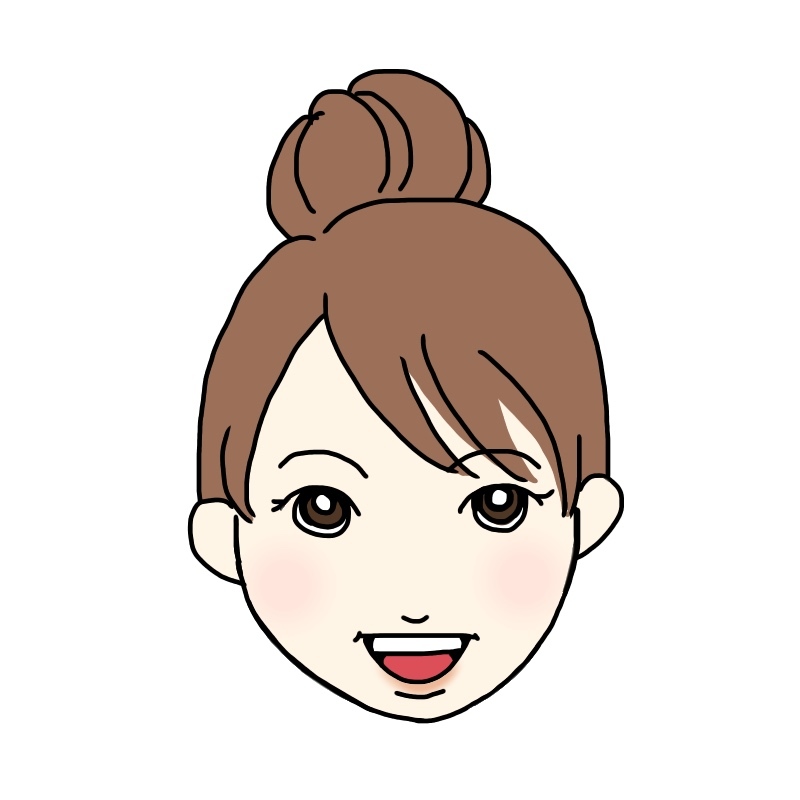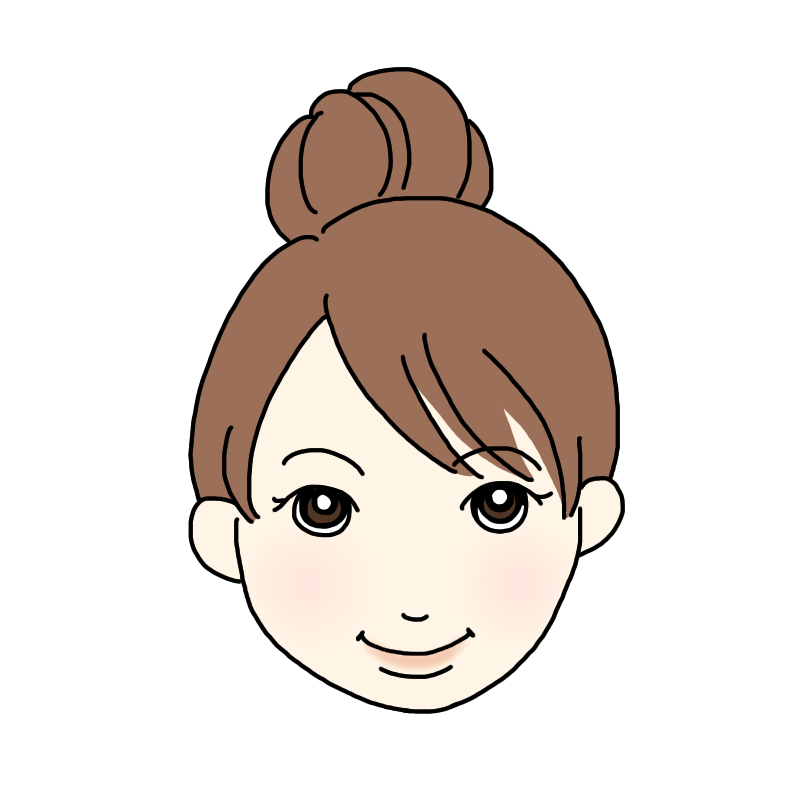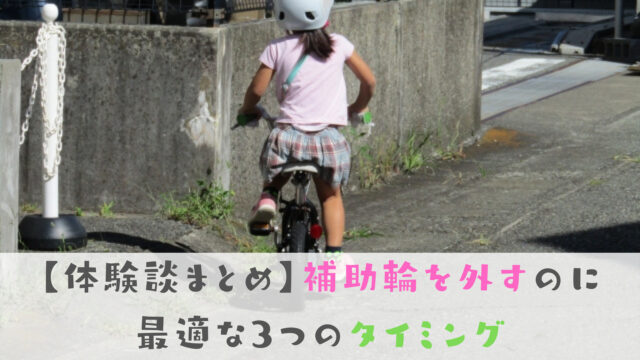この記事では、
- 幼稚園の探し方
- 幼稚園の選び方
- 入園までのスケジュール
を体験談を交えながらわかりやすく解説していきます。
これから幼稚園探しをしている方はぜひ参考にしてみてくださいね。探すのも選ぶのも本当に大変ですが、その先には楽しそうに登園する我が子の笑顔がありますよ!
この記事の幼稚園探しはいわゆるお受験幼稚園ではなく一般の公立・私立幼稚園の受験を前提に執筆しています。お受験幼稚園は全く別の対策が必要になりますのでご注意ください。
【幼稚園の探し方】5つのステップ

初めての幼稚園探し、一から取り組んでいく場合何から始めたらよいのかわからないですよね。
私も娘の通園に先立ち結構な数の幼稚園を見学しに行きましたが、どの幼稚園も個性が強く魅力的な部分が皆異なったのを思い出します。
そんな中でも自分の子供に合った幼稚園を選ぶために気を付けたい、幼稚園探しの5つのステップをわかりやすくまとめました。この手順で進めてみてくださいね!
- 情報収集をする
- 通園可能な幼稚園をリスト化する
- 気になる幼稚園を見学しに行く
- 運動会の未就園児競技に参加
- 入園説明会に参加する
情報収集をする
まずは情報収集!幼稚園探しの第一歩はここから始まります。
私は以下の4つの方法で近隣幼稚園の情報収集をしました。
- 自治体のホームページを確認する
- 役所の保育科で話を聞く
- 先輩ママに聞く
- 口コミサイトで調べる
自治体のホームページを確認する
まずは自治体のホームページを確認しましょう。公立幼稚園、私立幼稚園いずれも掲載されています。
どんな幼稚園がどのエリアにあるのか、ざっくりと把握することが可能です。リンクから幼稚園の公式サイトをまとめてチェックすることも可能です。
また、前年度に二次募集を行っているかも確認できるケースも多いので、人気のある幼稚園で倍率が高そうなどもチェックしておくのがおすすめです。
役所の保育科で話を聞く
次に、役所の保育科で実際に話を聞いてみるのがおすすめです。自治体のホームページに載っている以外の幼稚園や、去年の状況などをより詳しく教えてもらえます。
パンフレットなどを置いているケースも多いので、アナログの情報収集も可能です。
先輩ママに聞く
実は最も情報収集としておすすめなのが「先輩ママに聞く」ことです。
この方法の最大のメリットは、
- どんな雰囲気の子がどの幼稚園へ決めたのかがわかる
- 実際にどうやって幼稚園探しをしたのか聞ける
- 他に話を聞けそうな場所を紹介してもらえる
ことにあります。
口コミサイトで調べる
より多くの情報を集めたいという方には、口コミサイトでの情報収集もおすすめです。
ただ、こちらは匿名での投稿になるので信ぴょう性には若干欠けるケースも場合によってはあります。参考程度に見ておくのがおすすめです。
通園可能な幼稚園をリスト化する
大体の幼稚園を把握出来たら、次に自宅から通えそうな範囲の幼稚園をリストアップします。
幼稚園の通園方法は主に下記の3通り。
- 徒歩(自転車)通園
- 集団通園
- バス通園
この中から親子で3年間(兄弟がいる場合はそれよりも長く)できそうな通園手段を選び、通えそうな幼稚園に絞ります。
徒歩(自転車)通園
徒歩(自転車)通園は保護者が直接幼稚園まで子供を送る通園方法です。
- 幼稚園と家が比較的近い人におすすめ
- 子供と一緒に四季の変化を楽しめる
- 雨の日は少し大変
集団通園
集団通園は、保育者と担当の保護者が園児の集団を指定のコースで送る通園方法です
- 自然に体力がつく
- 他学年と交流できる
- 四季折々の自然に触れられる
バス通園
バス通園は最寄りのバス停まで保護者が送迎する通園手段です。
- 家が幼稚園から遠い家庭向け
- 子供同士のつながりが出来る
- 下に兄弟がいても比較的ラク
気になる幼稚園を見学しに行く
通えそうな幼稚園がわかったら、教育方針や雰囲気などを参考に見学の予約をします。
大体の幼稚園が毎年9~10月(早いところだと夏休みくらいから)に見学会を実施しているので、実際の雰囲気を肌で感じることができます。
この見学で大切なのは「子供も一緒に連れて行くこと」です。
話が聞きにくいから子供を置いていきたい気持ちもありますが、子供の直感は馬鹿にできません。「ここは嫌だ、ここは楽しい!」など、気持ちをハッキリ示しますよ。
運動会の未就園児競技に参加
これはやってもやらなくてもよいと思うのですが、可能であれば希望度の高い幼稚園は運動会の未就園児競技に参加してみるのがおすすめです。(ほとんどの幼稚園でやっています。)
行事などの特別な時の雰囲気や実際に通っている園児の普段の姿がよりわかるので、ぜひ楽しみながら参加してみてください!
入園説明会に参加する
気になる幼稚園を1~数個に絞れたら入園説明会に参加します。説明会では受験までの流れや具体的な入園費用、預かり保育の概要や今後の手続きなど詳しく話を聞けます。
説明会への参加は任意のところもあれば強制の幼稚園も多くあります。大切なことなので可能な限り参加しておきましょう。(合否に影響するかは幼稚園の方針次第)
事前申し込み制であったり先着順の幼稚園もあるので、早めに動きましょう!
【幼稚園を選ぶ前に】5つの注意点
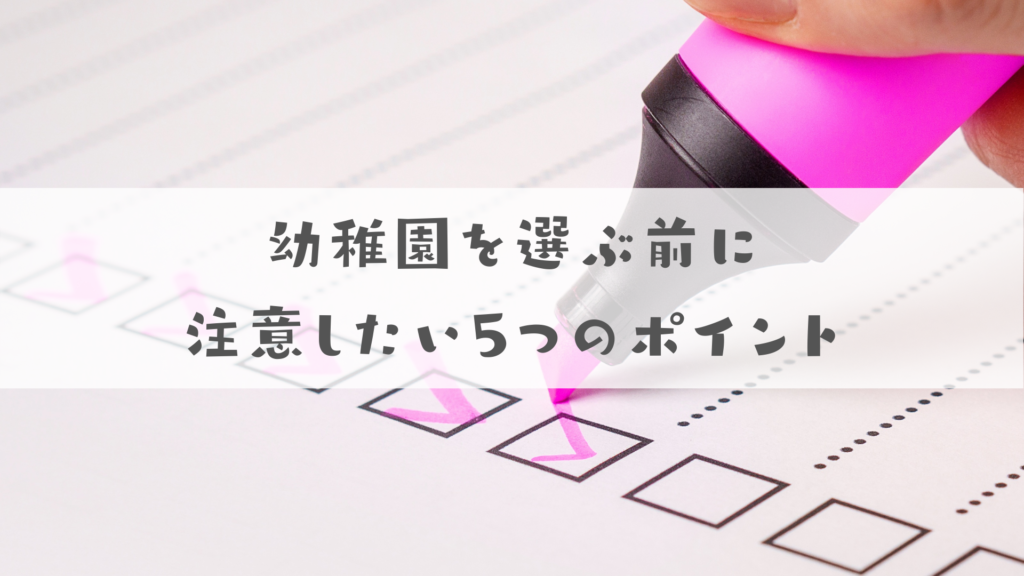
大体どのような幼稚園があるのかを把握できたら、次は選ぶ段階に入ります。
ただ、その前に注意しておきたい5つのポイントがあるので、詳しく解説していきます。
- 併願が出来ない
- プレスクール参加で枠が埋まる
- お受験要素が強い
- 入園が抽選で決められる
- 兄弟枠が多い
併願が出来ない
万が一第一希望の幼稚園に決まらなかった時のために、別の幼稚園を保険として受験しておきたいという方も多いと思います。
ただ、地域によっては併願が出来ないという事もあるので、各幼稚園の選考日時がかぶっていないかなどチェックしておきましょう。
また、幼稚園の倍率や条件や抽選で落とすケースがあるかなどの情報を収集して、併願の判断は慎重に行いましょう。
私の住んでいる東京都の場合は、私立幼稚園は11月1日に一斉受験を行います。大抵午前中に集中しているとどれほど時間がかかるかわからないケースが多いので、併願はかなり厳しいです。
実際に併願した人は先着順の第一希望A幼稚園と指定時間ギリギりまでに行ってもOKな第二希望B幼稚園を受けるなどしていましたが、A幼稚園に時間がかかってしまった場合B幼稚園は受けれないケースももちろんあります。
プレスクール参加で枠が埋まる
幼稚園によってはプレスクール(入学前に週1~2回程度短時間通園する制度)を実施しているところも多くあります。
幼稚園によってはこのプレスクールに参加した人を優先して入園させるところもあるので、人気のある幼稚園はプレスクール枠で定員が埋まってしまうことも。
お受験要素が強い
小学校受験を前提にした勉強中心のいわゆる「お受験幼稚園」の場合、今回の記事でご紹介した内容とは全く別の対策が必要となります。
幼児教室へ通ったり面接対策が必要になるケースも多いので、その幼稚園が受験メインの指導方針かを事前に確認しておきましょう。
入園が抽選で決められる
毎年定員を上回る応募のある人気幼稚園は、面接選考だけでなく抽選で入園者を決定するケースもあります。
こればかりは運なのでどうしようもないので、抽選入園の場合は二次募集を行っていそうな幼稚園も他に候補として用意しておくのがおすすめです。
兄弟枠が多い
小~中規模幼稚園の場合、兄弟枠が多い幼稚園が存在します。定員の半数くらいが兄弟で埋まってしまうケースもあるので、実際の定員ではなく兄弟枠を除いた大体の募集数を聞いておくのがおすすめです。
【幼稚園の選び方】7つのポイント

ここでは幼稚園を選ぶ7つのポイントをご紹介します。
- 2年保育or3年保育
- 私立幼稚園or公立幼稚園
- 教育方針
- お弁当or給食
- 延長保育の有無
- 園長や先生の雰囲気
- 幼稚園の設備や環境
2年保育or3年保育
2年保育or3年保育は幼稚園選びの一つのポイント。より子供と長く過ごしたいのか、早めに集団生活に慣れさせたいのか判断に迷うところです。
地域によっては4年保育という選択肢もあるので、子供の性格や家庭の状況を考えて何年保育にするのかを決めていきましょう。
私立幼稚園or公立幼稚園
私立幼稚園と公立幼稚園の一番の違いは昔は費用面の差でしたが、今は無償化により負担する金額はそこまで大差ないと思います。
私立幼稚園のほうがどちらかと言えば教育方針や指導内容に特色があったり、習い事などのオプションがあったりと、園生活の選択肢が色々あるという面が強いです。
教育方針
各幼稚園ごとに決められている教育方針は、短い言葉でありながら特色をうまく表している幼稚園選びの重要なポイントです。
教育方針をチェックした上で幼稚園を実際に見学してみると、園児の雰囲気がその通りになっているケースが多いので選ぶ上でとても参考になりますよ。
お弁当or給食
料理が苦手だったり働いているママにとては毎日のお弁当は辛いもの。負担を減らすためにも給食の有無や頻度をチェックして幼稚園選びの参考にしましょう。
私立幼稚園では完全給食のところもあります。また、給食が用意されていても利用者が少なく機能していない幼稚園もあるので、積極的に先生に質問して情報収集しましょう。
延長保育の有無
働くママにとって延長保育は必須!制度が存在しても定員オーバーで利用できなかったら意味がありません。また、園児数に対して預かり保育の枠が少ない幼稚園もあります。
定期利用の空き情報や都度利用でいつもどの程度埋まっているのかをチェックしておきましょう。
園長や先生の雰囲気
実際に子供と接することになる園長や先生方の雰囲気も幼稚園選びでは大切なポイント。特に園長先生は子供好きかそうでないかはハッキリとわかるので、ぜひチェックしましょう。
厳しめの先生が多いのか、優しくおおらかな先生が多いかで園児の雰囲気も違ってきます。見学の時は環境面だけでなく、指導面もぜひ気にしてみましょう。
幼稚園の設備や環境
幼稚園は子供が何年間も過ごす場所、設備や環境も幼稚園選びの大切なポイントです。
園庭の広さや教室の雰囲気、トイレの清潔感など設備は幼稚園によって全く異なります。実際に子供が通園することを想像して、どんな設備を喜びそうか考えてみましょう。
幼稚園探しから入園までのスケジュール
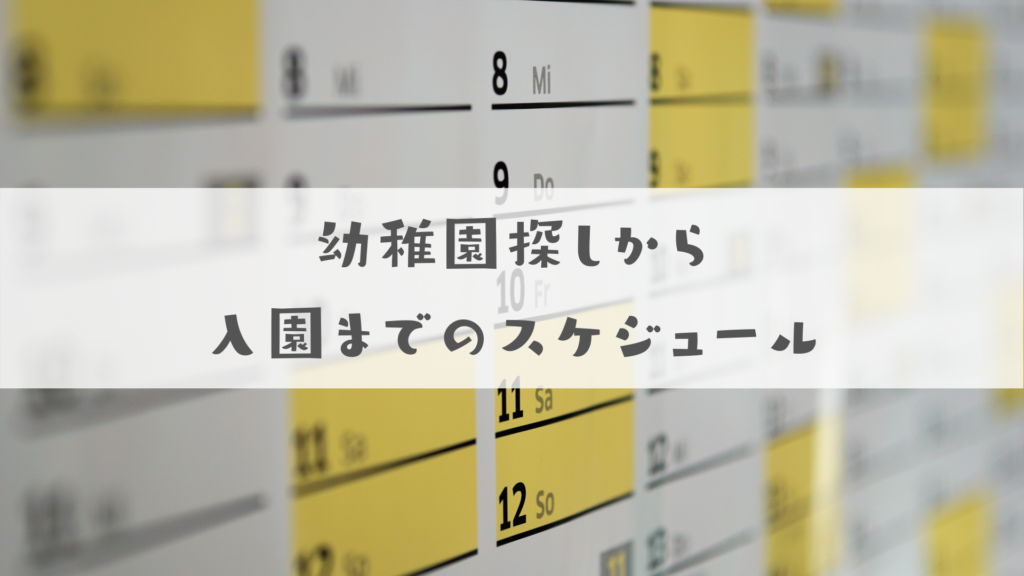
最後に幼稚園を探し始めてから入園までのスケジュールをわかりやすく図にまとめました。
ここでは2022年4月入園を前提にスケジュール例を紹介します!
三年保育の場合

三年保育の場合、2018年4月2日生まれ~2018年12月31日生まれの子供は3歳になる年の4月からスタート、2019年1月1日~2019年4月1日生まれの子供は2歳になる年の4月からスタートすることになります。
二年保育の場合

二年保育の場合は、2017年4月2日生まれ~2017年12月31日生まれの子供は4歳になる年の4月からスタート、2018年1月1日~2018年4月1日生まれの子供は3歳になる年の4月からスタートすることになります。
プレスクールや4年保育に通わせたい場合は、これより約1年弱スケジュールを前倒しすると考えてください!
幼稚園探しは納得いくまで親子で頑張ろう!
幼稚園の探し方&選び方のポイントをまとめます。
- 情報収集をする
- 通園可能な幼稚園をリスト化する
- 気になる幼稚園を見学しに行く
- 運動会の未就園児競技に参加
- 入園説明会に参加する
- 2年保育or3年保育
- 私立幼稚園or公立幼稚園
- 教育方針
- お弁当or給食
- 延長保育の有無
- 園長や先生の雰囲気
- 幼稚園の設備や環境
我が家の幼稚園探し体験談
私は幼稚園探しを始めるまで、
「給食があるとお弁当作らなくていいから楽だな…」
とか、
「近いほうが何かあった時に楽だなぁ…」
など、自分がいかに楽に育児をするかばかり考えていました。
けれども近くの幼稚園を見学しに行ってもなんだか娘には合いそうにない…ということで、最初は半径1キロ前後で探していたのをバス通園も視野に入れて半径3キロくらいまで広げて見学しに行きました。
そして、最終的に選んだのは、距離的に最も家から遠い約2.5㎞ほどある幼稚園。
遠いのは嫌だったのに、見学に行った時の園長先生のふるまいや子供への対応が本当に素晴らしく、娘も「この幼稚園がいい!」と意見が一致。
結果、実際に入園した今、娘は本当に毎日楽しそうに幼稚園へ通い、園長先生や担任の先生のこと、そしておともだちのことをお話ししてくれます。
幼稚園選びは本当に大変ですが、頑張った分だけ報われるということを絶対にお伝えしたいです。ぜひ後悔のないように納得のいくまで取り組んでみてくださいね!